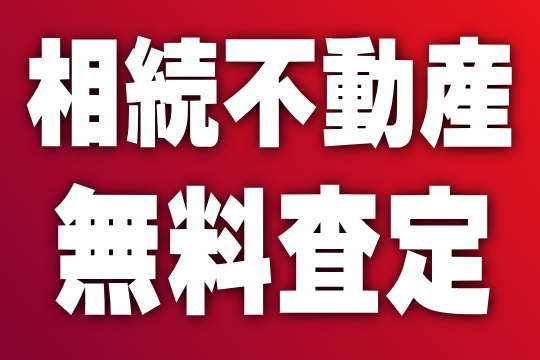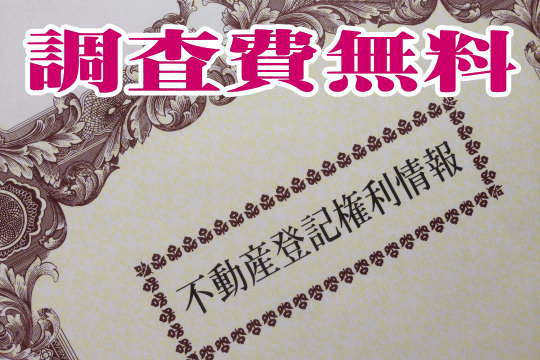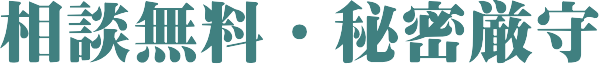今は幸せでも過去に「離婚」そして「再婚」をしたご夫婦は相続に気をつけてください! 入籍をしていない「事実婚」「内縁関係」のご夫婦は相続に気をつけてください。
離婚再婚をした夫婦、事実婚(内縁関係)のご夫婦の法定相続人は誰?
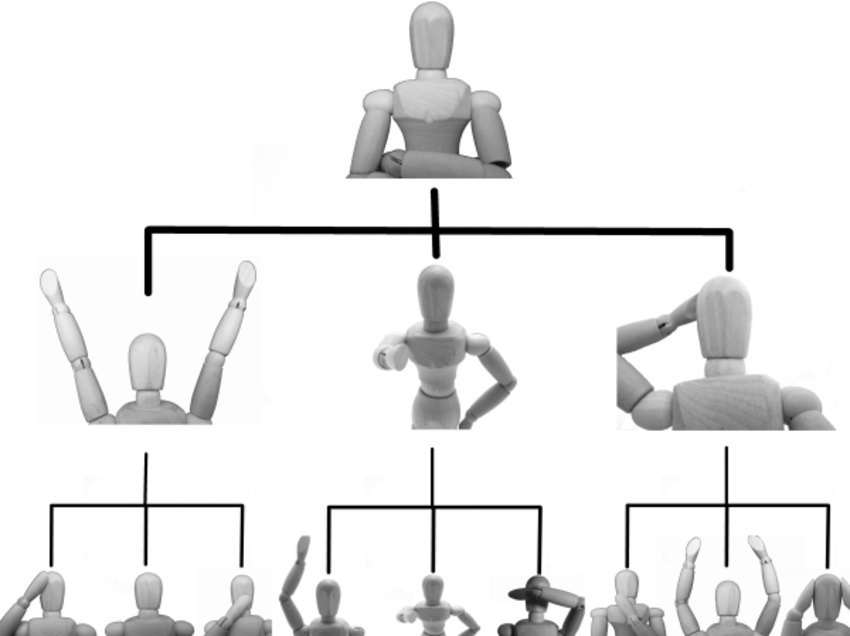
きっとあなたもうすうす気付いているかともいますが ・「離婚再婚」をしているご夫婦では、前夫・前妻との子供も法定相続人になります。 ・「子供のいない」ご夫婦では、亡くなった配偶者の親か兄弟姉妹か甥・姪かが法定相続人になります。
「離婚再婚」をしているご夫婦では、前夫・前妻との間にもうけた子供も法定相続人です
ご存知の通り、前妻・前夫の間にもうけた子供は法定相続人になります。 しかも大きな問題はこの「前夫・前妻との間にもうけた子供」ともう交流が無い?ことも珍しくないのです。特に成人するまではいろんな金銭的援助をしてきてあげたり面会もあったでしょうがその子供も成人して結婚独立したなら会う機会も減ります。(ひょっとしたら孫の顔も見たことがないかもしれませんね)また離婚した妻や夫が他の方と再婚をしていたならもう会うこともなくなっているかもしれません。 ただ「再婚後にできた子供」も「前妻・前夫との子供」も法律上の相続権の違いはありません。 (もちろん再婚相手の連れ子を養子縁組してあげている場合も同じ法定相続人です。) 「もう何十年も会っていない前妻・前夫との子供」と「再婚してもうけた子供・再婚相手の連れ子」とどちらの親子関係がより深いですか?正直 同じ子供であっても同じ愛情を持っていますか?自分の介護を任せることができるのはどちらですか? たとえ血の繋がっていない再婚相手の連れ子であっても、献身的に介護をしてきてくれているのではないですか?やっぱり別れた子供からすれば、出て行った「父」や「母」には良い感情を持っていないことも多いのです。なかなか「円満な離婚」は少なくドロ沼の離婚劇を間近で見てきた子供の傷も深いですから。
心の傷を背負っているかもしれない前妻・前夫の子供たちにとっての相続って 「もらえるものはもらいますよ!だってそれだ法律で決まっている相続なんでしょ!えっ?介護?それは私には関係ない話ですよ」 という考えになってしまっても仕方ないのではないですよね。
離婚の原因はどうあれそこにはいろいろな事情や経緯がありますから私が口を挟むわけにはいきません。ただ将来の「相続」を考えたらある程度対策が必要になります。なにも対策を打たないとこんな悲劇も起こりうるのですよ
先妻の子供から「今の家から出て行け」と言われたら?
こんなトラブルが非常に多かったせいなのか?新たに民法が改正予定で「配偶者居住権」が明記されることになりました。でも、それでも万全ではなくやはり相続対策をしてくださいね。
 相続対策専門士江本
相続対策専門士江本実は私の両親も互いに前夫・前妻がいる再婚で異父兄弟・異母兄弟がいます。そしてこれが相続の手続きに大きな障害となっています。 相続のプロと自負している私ですが正直ギブアップしていますから偉そうなことは言えませんね。でも対策をするのは親にしかできないので子供は無力です。
前妻・前夫の子供には1円も相続させたくない?
意外とこの「前妻や前夫との間にもうけた子供に今の財産を渡したくない!」という方が少なくありません。 しかし、何年も?何十年も交流が一切無い前夫・前妻との子供であってもりっぱな法定相続人であることはしっかりと認識しておいてくださいね。ただ相続対策を講ずれば「前夫・前妻との子供に相続させない」ことも不可能ではありませんし、できるだけ少なくすることは可能です。
ちょっとグレーだけど「必要な相続手続き」をできるだけ無くす
あまり大っぴらには言えないのですが 「たとえ子供であっても親の財産を調べるのは至難の業」なんです。 ですから隠せない財案(不動産・株)を隠しやすい財産(現金・生命保険)に換えておくことが大事です。
■子供が生前の親の銀行預金の残高を調べるには 子供が生前の親名義の預金の状況を調べようと思えば調べる事はできます。 まずは法定相続人であることを証明する書類(戸籍謄本など)を用意して各金融機関に親名義の預金の残高証明や取引履歴を請求することができます。ただこれはどの銀行で?さらにどの支店で?まで必要なんです。 分からない場合は予想さえる近所の銀行を片っ端から調べることになりますがこれはかなり難しいです。 この意味 わかりますか?
■生命保険の受け取りを指定しておく 相続対策に生命保険があります。 相続税対策にもなるのですがここでは割愛します。 要は1億のお金を1億の生命保険受という形に換えておくことです。 裁判沙汰にまでなって生命保険の存在にまで気づかれればちょっと危険ですが、生命保険金は民法では相続財産ではありません。ですから愛人を生命保険受取人にしたケースみたいに後から取り返すのはなかなか難しいのと同じです。 この意味 わかりますか?
■要は相続手続きが無い様にすることが大事 不動産の名義を変える相続登記 預金の解約手続き などなど相続手続きには法定相続人全員の署名捺印のある遺産分割協議書が必要になります。 そうなれば前妻前夫の子供も法定相続人なりハンコを貰わなければいけません。 だからできるだけ相続手続きが不要になるようにしていかないといけないのです。 この意味 わかりますか?
子供のいない夫婦ではどちらかが亡くなるとその相手側の「親」or「兄弟姉妹」or「甥・姪」が法定相続人になってきます
「子供のいない夫婦」の場合はどちらかが先に亡くなった場合は原則こんな流れになります。 ①亡くなった配偶者の親(法定相続割合(1/3) その親が亡くなっていれば次順位として ②亡くなった配偶者の兄弟姉妹(法定相続割合1/4) その中で亡くなっている方がいればその相続権を継承するのが ③亡くなった配偶者の甥や姪 となります。
入籍していない事実婚(内縁関係)の妻や夫には相続権はありません
法律の世界はある意味非情です。いくら長年本当の夫婦のように暮らしてきても戸籍上の夫婦でなければ相続権はありません。
「離婚・再婚した夫婦」「子供のいない夫婦」の相続対策
では少し具体的な相続対策を考えてみましょう まずは典型的な子供のいない夫婦の相続トラブルのご紹介しておきます。
「離婚・再婚した夫婦」の相続対策

まず、前提条件として相続税がかかるほどの財産であるかどうかで少し難易度がが変わってきます。 相続税の基礎控除額は『3000万円+法定相続人×600万円』です。これを超えるような方なら具体的対策は弁護士にも相談すべきかと思います。相続税の申告は前妻・前夫の子供も含んだ相続人全員で行なわなければいけませんし、もしそこで遺産隠しをすれば脱税です。税務署には強制的捜査権もありますから気をつけないといけません。ただ、多くの方はこの相続税基礎控除額以内の遺産相続なのですから「こんな方法もありますよ?」とご参考にしてみてください。
まずはとにもかくにも遺言書!しかも公正証書遺言で!
とにかく遺言書で亡くなった方の遺志を証明する方法を確保しておかなければいけません。 遺言書には自分で書く「自筆証書遺言」と公証役場に出向いて作成する「公正証書遺言」がありますが必ず「公正証書遺言」で作成しておくべきです。「自筆証書遺言」には費用もかからず手軽に書ける利点はありますが、法律的に不備があったりすると無効という大きな短所もありますがさらに最大の短所は・・・?
この「検認」という手続きのために「前妻・前夫の子供」にも家庭裁判所から連絡が行きますし、遺産の内容も知られます。なにより何十年も会っていない「前妻・前夫の子供」の『寝た子を起こしてしまう?』ということにもなりかねないのです。
しかし、公正証書遺言ではこの『検認』という手続きは不要です
まして、この公正証書遺言書さえあれば「登記名義変更」「預金解約」など相続手続きも粛々と進めることができます。確かにわざわざ公証人役場に出向いたり、作成費用もかかります。できれば司法書士などの専門家の力も借りたほうがよいと思います。それでもやはり公正証書遺言書の作成を強くお勧めします。
遺留分をどうする?
ただ遺言書でも完全ではありません。 相続ではいくら「1円も相続させたくない相手」であっても遺留分という最低限保証された相続できる権利があります。
ただこの遺留分の請求は「自分が遺留分を侵害されたことを知ってから1年間」または「相続が発生してから10年間」以内に請求しなければいけません。このあたりを踏まえて対策を考えてみてください。 (ここではこれ以上のことをお話しするのはやめておきますね。)
しかし、遺言書を書くことに大きな抵抗がある方も多いのも事実
「書いて!」とお願いしてもなかなか書いてくれないのが遺言書です。 おそらく今これを読んでいるあなたは「遺言書を書く側」ではなく「遺言書を書いて欲しい側」ではないですか? 遺言書を書きたくない人に遺言書を書かせることはできません。あまり無理強いするとますます意固地になって拒まれますしそのことで大きな喧嘩にもなりかねません。
ではどうするか? ならば極力相続手続きが不要になるようにしなければいけません。 全ての相続手続きには相続人全員の了承が必要ですし、だれかひとりでも反対ならばできません。そのためにできるだけ相続手続きの要らないようにしておく必要があります。 相続手続きの大きなものに「不動産の登記名義変更」があります。できれば売却して換金化しておくこともお勧めします。(もう少しお話ししておきたいこともありますがここではここまでにしておきます。) またちょっと普通の生命保険ではなく相続対策用の生命保険商品もあります。死亡保険受け取り金は税法上はみなし相続財産ですが民法上は相続財産ではありません。死亡保険金を妻や夫や遺産を優先的に相続させたい子供にしておけばよいのです。もちろん極端なやり方は「遺留分侵害」にもなりかねないので気をつけてください。
他にいろいろな方法も考えられますが、ここではあまりおおっぴらにはお話できません。 ただ、ヒントは税務署みたいに強制捜査権が無いのだから、たとえ自分の親であっても親の死後に他の誰かがその財産状況を調べ上げることは非常に難しく煩わしい!?ということだけお話しておきます。
もしも相続税がドカンとかかるほどの財産があるなら?
ここまでは「遺産の分け方」の問題でしたが、こと相続税がかかるほどの遺産ならばかなり難易度が上がります。相続でもめると有利な相続税の特例措置利用できないことも考えられます。あるいは莫大な財産を築き上げたご夫婦の場合は相手は弁護士を立ててくるかもわかりません。そんなことが考えられる場合は仕方ありません。遺留分を考慮した遺産分割案の遺言書がよりベターな選択かもしれません。
「子供のいない夫婦」の相続対策

「子供のいない夫婦」の相続対策もほぼ前述の「離婚・再婚をした夫婦」の相続対策とよく似ています。
「子供のいない夫婦」の相続割合は、配偶者(妻or夫)と 亡き配偶者の親(義両親)で法定相続割合は1/3 既に義両親が亡くなっていれば次順位の義兄弟姉妹で法定相続割合は1/4 確かに法定相続割合はかなり小さくなります。ただいくら法定相続割合が少なくとも相続手続きは各相続人全員の了承が必要なことはしっかりと理解しておいて下さい。相続手続きでなにをするにも義実家の顔をうかがわないといけないのは残された妻や夫にとってはかなり気の重いことです。 もし、そこでちょっとした争いでもあれば1周忌や七回忌などの法事も自分の兄弟姉妹抜きで行なわないといけなくなるかもしれません。
ですからやはり遺言書が重要です。 そうすれ亡き夫や妻の親兄弟の意思など関係なく相続手続きを進めることだできます。 義兄弟姉妹に遺産の内容を知られることなく粛々と相続手続きを済ませることもできるのです。
義理の兄弟姉妹には遺留分は認められていない
通常は義両親はすでに亡くなっていることが多いと思いますから、「子供のいない夫婦」の相続の話は妻や夫の残された配偶者と義理の兄弟姉妹(またはその甥や姪)が法定相続人に入ってくる場合がほとんどだと思います。 でも、遺言書さえあればこの方たちを遺産相続から廃除できます。 なぜなら通常は最低限保証された相続する権利の遺留分が兄弟姉妹には認められていないので、遺言書の内容が強く絶対になるからです。
とにかく遺言書だけでも作成しておく(公正証書遺言がおすすめ)
子供のいない夫婦の場合の法定相続人は義理の兄弟姉妹(さらに義理の甥や姪の場合もある)であることはご承知の通りです。 だからこそ遺留分のない義理の兄弟姉妹たちには遺言書さえ書いておけば安心なのでです。 遺言書さえあればこんなトラブルから回避できるのです。
普通の優しい口調でかなりエゲツナイ主張かも? たとえ一切交流が無くても法律上自分に相続権があるとわかったら「もらえるものはもらいますよ!当然でしょ!」という甥や姪たちの主張 お金の魔力は恐ろしいのです。 だからこそこんな風に公正証書遺言があれば他の兄弟姉妹(または甥や姪)は手も足も出ないのです。
ひょっとしたら籍を入れていない内縁関係で子供のいない夫婦の場合もあるでしょう。 自分に子供はいないが相手に子供がいる場合もあります。 ちょっと遺言書ではないですがご参考になるかと思います。
公正証書遺言書の作成は弁護士か司法書士にしますが、費用面からはやはり司法書士が賢明でしょう。 自分で書く自筆証書遺言では家庭裁判所の検認手続きが必要でこれは義理の兄弟姉妹たちへ通知が届きますし、そこで詳しい遺産の内容がバレてしまいます。その点、公正証書遺言では検認手続きは不要で他の義理の兄弟姉妹は関係なく粛々と相続手続きができます。 もし司法書士のお知り合いがいない場合はおすすめのホームページサイトも紹介しておきます。 相談は無料ですから、気軽に問い合わせてみてはいかがでしょうか?
相続問題に強い弁護士が集まっているサイト【相続弁護士ナビ】

相続弁護士ナビでは相続問題に強い弁護士がたくさん登録されています。 きっとあなたのお近くの心強い味方の弁護士が見つかるでしょう。
相続に強い弁護士ならきっとなにか良い提案をしてくれると思います。
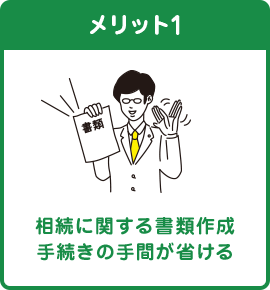
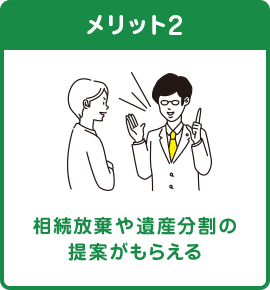

でも、先祖伝来の土地建物など不動産は慎重になってください
たしかに夫婦二人だけで助け合って築いてきた財産なら残された妻などがすべて相続するのも当然かもしれません。でも、それが先祖伝来の代々引き継がれてきた財産であったらちょっと気をつけないといけないこともあります。
それは、夫が亡くなって妻が相続した遺産、今度は妻が亡くなった時には妻側の家系に引き継がれていってしまうことです。 「先祖代々引き継がれてきた財産」と「夫婦二人で築き上げた財産」ではちょっと想いが異なるように感じるのは私だけでしょうか? 夫が妻に「この遺産は◎◎家先祖からの財産だから、俺亡き後にもしお前になにかあったなら俺の甥や姪に相続させるよう遺言書をちゃんと書いておいてくれ!」というお願いもできますが、えてして人間は突然亡くなるものですしひょっとしたらそんなことも覚えていない認知症になってしまうこともあります。
子供のいない夫婦の相続や財産分与についてはこちらでもご説明しています。 参考:子なし夫婦の相続・財産分与は義理兄弟も相続人!だから遺言書だけでも

こんなわずかな遺産でドロドロの裁判沙汰の相続トラブルになる!少ない遺産相続ほどよくもめるという現実をご存知ですか?
<<遺産相続トラブルでもめる兄弟や家族の特徴のまとめ【ワースト5】に戻る
「離婚・再婚した夫婦」「子供のいない夫婦」の相続について私とご一緒に考えてみませんか?

なにもしなければどんどん状況は悪くなるばかりです。誰かが行動を起こさないとなにも変わりません。私たちはそんなあなたのお手伝いをするためにさまざまサービスをご用意しています。